 |
| 大小天守閣(大天守約30m、小天守約19m) |
 |
| 首掛石(熊本城築城の際、強力横手の五郎が首にかけて運んだと伝えられる石) |
 |
宇土櫓(重要文化財)
第三の天守とも云われ、三層五階、入母屋屋根を二段に重ね、最上階の望楼は高欄になっており、大天守とは全く異なった風格をもっている。 |
 |
| 大天守閣から見下ろす熊本市内 |
| 熊本城 |
|
| 場 所 |
熊本市本丸1番1号 |
| 訪問日 |
2回目/2006年3月21日(晴れ)
初回/1995年3月(晴れ) |
| 歴 史 |
別名:銀杏城
築城年:応仁年間(1467〜1469年)
築城者:出田秀信
形状:平山城
熊本城は、1588年(天正16年)肥後半国の領主として熊本に本拠を置いた加藤清正によって築かれた。
築城は1601年(慶長6年)から7年余りの年月をかけ、1607年(慶長12年)に完成。
名将の加藤清正が、その実戦経験をもとに築城技術のすべてを投入して築きあげた難攻不落の城として世に広く知られている。
城郭は周囲9Km(築城当時)、広さ約98万m2で、その中に天守3、櫓49、櫓門18、城門29を持つ雄大な構えで、なかでも「武者返し」と呼ばれる美しい曲線を描く石垣は特に有名。
この熊本城築城に従事した石工は、加藤清正が近江(滋賀県)から連れてきた近江石工によるものだそうだ。
熊本城は以後、加藤家2代(44年)、細川家11代(239年)の居城となる。
1877年(明治10年)の西南の役に際しては、薩摩軍を相手に50日余も籠城し、難攻不落の城として真価を発揮した。しかし薩摩軍総攻撃の2日前、原因不明の出火により天守閣など主要な建物を焼失し、宇土櫓ほか12棟が残り、国の重要文化財となっている。
現在の天守閣は1960年(昭和35年)熊本市によって再建されたもの。 |
| アクセス |
熊本駅前から 市電 熊本城前まで10分 |
| 問合せ先 |
096-352-5900 |
| 開城日 |
年中無休(12月29〜31日は休み)
8:30〜16:30(4〜10月は17:30まで) |
| 入城料 |
500円 |
|
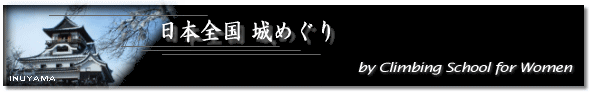
 【写真】水前寺公園
【写真】水前寺公園


